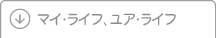涙もろくなったのはいつ頃からだろうか。二十代で涙を流したのは父親を亡くした時くらいしか記憶がない。もともと喜怒哀楽を表現するのが得意でないのだが、自分は冷たい人間ではないか、と考えたこともあった。「人前で涙は見せてはいけない」とか「顔で笑って、心で泣いて」と言われた時代に育ったこともあるのかもしれない。高校生の時に「ある愛の詩」という絵に描いたようなお涙頂戴のラブストーリー映画を観て、不覚にも涙が出そうになり、思わずこらえたことがある。そして、フランシス・レイの音楽があまりに甘く切なくて、つい感情移入をし過ぎたためなのだ、と自分に言い訳しながらも、とても恥ずかしく感じたのを覚えている。
五十歳を迎える頃からか、しだいに涙もろくなったように思う。若い頃の傲慢さや自意識、自己中心的な考えが、様々な経験や人との出会いによって人生の機微に触れて、変わっていくのだと思う。涙ということで言えば、怒りや悔し涙であったのが、共感(悲しみ)や感謝の涙となっていくのだ。言い換えれば年月を経て、少しは人の悲しみに共感でき、人の情をありがたく感じることができるようになった、と言えるだろう。
最近、テレビでスポーツ選手やテレビ出演者が涙を流す姿をよく見かける。公共の場で素直に感情を出せるのはよい時代なのかもしれない。しかし涙と感動の安売りと感じられることも多く、複雑な気持ちである。
小津安二郎監督の映画に出演していた笠智衆は「明治生まれの男が泣くことはめったにない」と自ら泣くシーンは拒否していたそうである。小津監督の「東京物語」では長年連れ添った妻を亡くす老人役で登場し、終始穏やかで感情を露わにすることない明治の男を演じた。妻の死を覚悟し、受け入れていくその姿は私たちの胸を強く打った。涙で表現することが安直なことであると思えるほど、その悲しみや喪失感の静かな表現に心を揺さぶられる。涙以上に悲しみを伝えるものがあることを教えられた。

- 2019年12月 (1)
- 2019年11月 (4)
- 2019年10月 (5)
- 2019年9月 (4)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (5)
- 2019年6月 (4)
- 2019年5月 (4)
- 2019年4月 (5)
- 2019年3月 (4)
- 2019年2月 (4)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (4)
- 2018年11月 (4)
- 2018年10月 (5)
- 2018年9月 (4)
- 2018年8月 (4)
- 2018年7月 (5)
- 2018年6月 (4)
- 2018年5月 (5)
- 2018年4月 (4)
- 2018年3月 (4)
- 2018年2月 (4)
- 2018年1月 (5)
- 2017年12月 (4)
- 2017年11月 (4)
- 2017年10月 (5)
- 2017年9月 (4)
- 2017年8月 (5)
- 2017年7月 (4)
- 2017年6月 (4)
- 2017年5月 (5)
- 2017年4月 (3)
- 2017年3月 (5)
- 2017年2月 (2)
- 2017年1月 (2)
- 2016年12月 (3)
- 2016年11月 (2)
- 2016年10月 (2)
- 2016年9月 (2)
- 2016年8月 (3)
- 2016年7月 (4)
- 2016年6月 (4)
- 2016年5月 (5)
- 2016年4月 (4)
- 2016年3月 (5)
- 2016年2月 (4)
- 2016年1月 (4)
- 2015年12月 (4)
- 2015年11月 (4)
- 2015年10月 (4)
- 2015年9月 (5)
- 2015年8月 (4)
- 2015年7月 (4)
- 2015年6月 (5)
- 2015年5月 (4)
- 2015年4月 (4)
- 2015年3月 (5)
- 2015年2月 (4)
- 2015年1月 (4)
- 2014年12月 (4)
- 2014年11月 (4)
- 2014年10月 (4)
- 2014年9月 (5)
- 2014年8月 (4)
- 2014年7月 (4)
- 2014年6月 (5)
- 2014年5月 (4)
- 2014年4月 (5)
- 2014年3月 (4)
- 2014年2月 (4)
- 2014年1月 (4)
- 2013年12月 (4)
- 2013年11月 (4)
- 2013年10月 (5)
- 2013年9月 (4)
- 2013年8月 (4)
- 2013年7月 (5)
- 2013年6月 (4)
- 2013年5月 (4)
- 2013年4月 (5)
- 2013年3月 (4)
- 2013年2月 (4)
- 2013年1月 (4)
- 2012年12月 (4)
- 2012年11月 (4)
- 2012年10月 (5)
- 2012年9月 (4)
- 2012年8月 (4)
- 2012年7月 (5)
- 2012年6月 (4)
- 2012年5月 (5)
- 2012年4月 (4)
- 2012年3月 (4)
- 2012年2月 (4)
- 2012年1月 (4)
- 2011年12月 (4)
- 2011年11月 (5)
- 2011年10月 (4)
- 2011年9月 (4)
- 2011年8月 (5)
- 2011年7月 (4)
- 2011年6月 (4)
- 2011年5月 (5)
- 2011年4月 (4)
- 2011年3月 (5)
- 2011年2月 (1)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |