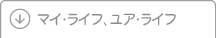5月16日、湘南アマデウス合奏団の第36回定期演奏会を聴きに行った。会場は鎌倉芸術館小ホールである。このホールは、旧松竹大船撮影所(現在は、鎌倉女子大のキャンパスになっている)のすぐ近くに建っていて、界隈には小津安二郎や笠智衆や原節子が撮影の合間に愛用したという食堂や喫茶店が残っている。ここで何度かコンサートを聴いているが、来るたびに古き良き日本映画の黄金期に思いが及び、耳にする楽曲に別の彩りが加わる。
湘南アマデウス合奏団の方たちには、藤沢育成会はいつもたいへんお世話になっている。姉妹楽団の湘南アマデウス合唱団の方たちと一緒に毎年、湘南あおぞらでクリスマスコンサートを開いていただいている。「アマデウスコンサート」の愛称で親しまれているが、音楽を聞かせてもらうだけでなく、クリスマスケーキもプレゼントしていただき、年末の恒例行事として利用者の方たちは毎年たいへん楽しみにしている。
 今回の鎌倉芸術館小ホールでのコンサートは、収益金の一部を藤沢育成会に寄付していただけることになっており、ご厚情に感謝しつつ、いつもの通り小津監督の顔などを思い浮かべながらプログラムに耳を傾けた。
今回の鎌倉芸術館小ホールでのコンサートは、収益金の一部を藤沢育成会に寄付していただけることになっており、ご厚情に感謝しつつ、いつもの通り小津監督の顔などを思い浮かべながらプログラムに耳を傾けた。
曲目は、モーツァルト「ドンジョヴァンニ 序曲」「ピアノ協奏曲第23番」、休憩を挟んでベートーヴェン「交響曲第2番」であった。中々通好みの渋い選曲に、モーツァルトの楽曲を中心に演奏活動を続けている同合奏団の矜持を感じた。演奏会全体の感想は、親しくさせていただいている楽団員の方たちに直接お伝えしようと思うが、ここではベートーヴェン「交響曲第2番」を聞きながら、思いめぐらしたことを記してみたい。
演奏会のプログラムでも触れていたが、「交響曲第2番」はベートーヴェンの難聴の症状が進み、完全に音の世界を失う危機のさなかで作曲された。有名な「ハイリゲンシュタットの遺書」が書かれたのは、「交響曲第2番」の完成のすぐ後である。「ハイリゲンシュタットの遺書」は、甥のカールと弟のヨハンに宛てて書いた手紙で、投函されないままベートーヴェンの手元に残され作曲家の死後に発見された。音の世界を失うことへの恐怖と失恋の苦しみが赤裸々に綴られており、かつては遺書と見られていたが、最近の研究では苦悩を越えて新たな生へ向かう旅立ちの書ではないかと言われている。2年前にウィーンを訪れた際に、ベートーヴェンハウスに立ち寄り、展示されている「ハイリゲンシュタットの遺書」の実物を見ることができた。しばしの間、直筆に見入り「苦悩の人、ベートーヴェン」に思いを馳せた。
最近、伊藤亜紗著『目の見えない人は世界をどう見ているか』という本を読んだ。題名に惹かれてすぐに取り寄せたのだが、予想に違わずとても刺激的な本だった。題名から察して、著者は視覚障害者の支援に関わる福祉関係者かと予想したのだが、著者略歴を見ると「東京工業大学リベラルアーツセンター准教授、専門は美学、現代アート」とある。伊藤亜紗さんは高校生の頃、本川達夫の『ゾウの時間ネズミの時間』を読んで生物学者を目指したそうだ。本川さんのこの本は、動物の時間感覚はそのサイズによって全く異なるということを実に説得的に論証して、20年以上前に出版された当時たいへん話題になった。ゾウの感じる一秒とネズミの感じる一秒は全く違っているというのである。この説は、大方に受け入れられ、『ゾウの時間ネズミの時間』は今でもロングセラーを続けている名著である。 伊藤亜紗さんは本川説に導かれて生物学者を目指して大学に入ったが、3年生の時に方向転換し、美学の研究者への道を進む。美学というのは、美しさとは何かと言うことを言葉でなんとか表そうとする、哲学の一部門をなす学問だが、伊藤亜紗さんは生物学者を一時は志向しただけあって、ユニークなアプローチを美学の研究に持ち込んでいく。美学は美しさという感性について追究するわけだが、感性は結局身体の働きであり、芸術作品は身体に密接にかかわっている。とすると美学の究極形態は、「体について体で理解する」ということではないか。
伊藤亜紗さんは本川説に導かれて生物学者を目指して大学に入ったが、3年生の時に方向転換し、美学の研究者への道を進む。美学というのは、美しさとは何かと言うことを言葉でなんとか表そうとする、哲学の一部門をなす学問だが、伊藤亜紗さんは生物学者を一時は志向しただけあって、ユニークなアプローチを美学の研究に持ち込んでいく。美学は美しさという感性について追究するわけだが、感性は結局身体の働きであり、芸術作品は身体に密接にかかわっている。とすると美学の究極形態は、「体について体で理解する」ということではないか。
そして、大事なのは身体一般ではなく、個々の身体ではないか。そう考えて、伊藤亜紗さんの前に現れたのが「見えない人」の存在だった。私たちは情報の8割から9割を視覚に頼って得ているという。五感のうちで視覚は特権的な地位にあり、西洋では都市の作りまでもが目の快楽のために作られていると思えることもある。それでは、私たちがもっとも頼っている視覚という感覚を取り除いてみると、世界のとらえ方はどうなるのか?
「視覚を使わない体に変身してみたい」
伊藤亜紗さんは、この思いに強く駆られ、ユニークな著作『目の見えない人は世界をどう見ているか』を著わすことになった。この本は、伊藤亜紗さんが4人の視覚障害をもつ人にインタビューをして、それをもとに構成されている。伊藤さんは幸か不幸か視覚を「持ってしまって」いるので、「視覚を使わない体に変身してみたい」と思ったら、視覚を持たない人たちに話を聞いてみるしかないわけだ。「空間」「感覚」「運動」「言葉」「ユーモア」の各章に分かれて、伊藤さんが聞き取り再構成した「見えない世界」が手に取るように展開される。「視野をもたないゆえに視野がひろがる」「見えない人の色彩感覚」「全盲でも絵画鑑賞できるんじゃないか」など小見出しを拾ってみただけでも、この本のユニークさが分かっていただけるだろう。
鎌倉芸術館小ホール、指揮者がタクトを振りおろし、ベートーヴェンの「交響曲第2番」が始まった。一つの思いがひらめいた。
『ベートーヴェンを「聴覚を使わない体」になった人ととらえるとどうなるか』
もちろん、「視覚を使わない体に変身してみたい」という伊藤亜紗さんの思いにインスパイアされて、この思いが浮かんだのだった。
「作曲家にとって一番大切な聴覚を失った悲劇の人。その障害を乗り越えて、偉大な作品を生み出した苦悩の天才」
ベートーヴェンについての大方のイメージはこうしたもので、私もこのステロタイプなベートーヴェン像を持っていたと思う。しかし、ベートーヴェンは耳が不自由だったのか?むしろ、聴覚を失うことによってベートーヴェンは、途轍もなく自由な音の世界を得たのではないか。耳が聞こえなくなって、ベートーヴェンは一切の世俗の雑音を聞く必要がなくなった。「聴覚を使わない体」の人、ベートーヴェンは自らの中から湧き上がり、体を駆け巡る音の世界だけに生きることができるようになったのである。そして、その音の世界は人類史上稀にみる深さと美しさを湛えていた。自らの内に鳴り響く音をひたすら記譜し続け、音楽の形にして後世に残してくれたのが、ベートーヴェンだったのである。聞こえる人には決して味わうことができない、充溢した音の世界とともにベートーヴェンは人生を過ごしたのではないか。それは不幸とか不自由とかいう言葉とは無縁だったはずである。
こう考えると「交響曲第2番」は、今までと全く違った響きで私の耳に届いてきた。聴覚を失う恐怖におののくベートーヴェンではなく、「聴覚を使わない体」を縦横に楽しむベートーヴェン。「交響曲第2番」を楽しみ、聞き終わってその余韻が、人生の幸せの形は無数にある、という当たり前の真実を改めて教えてくれた。

- 2019年12月 (1)
- 2019年11月 (4)
- 2019年10月 (5)
- 2019年9月 (4)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (5)
- 2019年6月 (4)
- 2019年5月 (4)
- 2019年4月 (5)
- 2019年3月 (4)
- 2019年2月 (4)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (4)
- 2018年11月 (4)
- 2018年10月 (5)
- 2018年9月 (4)
- 2018年8月 (4)
- 2018年7月 (5)
- 2018年6月 (4)
- 2018年5月 (5)
- 2018年4月 (4)
- 2018年3月 (4)
- 2018年2月 (4)
- 2018年1月 (5)
- 2017年12月 (4)
- 2017年11月 (4)
- 2017年10月 (5)
- 2017年9月 (4)
- 2017年8月 (5)
- 2017年7月 (4)
- 2017年6月 (4)
- 2017年5月 (5)
- 2017年4月 (3)
- 2017年3月 (5)
- 2017年2月 (2)
- 2017年1月 (2)
- 2016年12月 (3)
- 2016年11月 (2)
- 2016年10月 (2)
- 2016年9月 (2)
- 2016年8月 (3)
- 2016年7月 (4)
- 2016年6月 (4)
- 2016年5月 (5)
- 2016年4月 (4)
- 2016年3月 (5)
- 2016年2月 (4)
- 2016年1月 (4)
- 2015年12月 (4)
- 2015年11月 (4)
- 2015年10月 (4)
- 2015年9月 (5)
- 2015年8月 (4)
- 2015年7月 (4)
- 2015年6月 (5)
- 2015年5月 (4)
- 2015年4月 (4)
- 2015年3月 (5)
- 2015年2月 (4)
- 2015年1月 (4)
- 2014年12月 (4)
- 2014年11月 (4)
- 2014年10月 (4)
- 2014年9月 (5)
- 2014年8月 (4)
- 2014年7月 (4)
- 2014年6月 (5)
- 2014年5月 (4)
- 2014年4月 (5)
- 2014年3月 (4)
- 2014年2月 (4)
- 2014年1月 (4)
- 2013年12月 (4)
- 2013年11月 (4)
- 2013年10月 (5)
- 2013年9月 (4)
- 2013年8月 (4)
- 2013年7月 (5)
- 2013年6月 (4)
- 2013年5月 (4)
- 2013年4月 (5)
- 2013年3月 (4)
- 2013年2月 (4)
- 2013年1月 (4)
- 2012年12月 (4)
- 2012年11月 (4)
- 2012年10月 (5)
- 2012年9月 (4)
- 2012年8月 (4)
- 2012年7月 (5)
- 2012年6月 (4)
- 2012年5月 (5)
- 2012年4月 (4)
- 2012年3月 (4)
- 2012年2月 (4)
- 2012年1月 (4)
- 2011年12月 (4)
- 2011年11月 (5)
- 2011年10月 (4)
- 2011年9月 (4)
- 2011年8月 (5)
- 2011年7月 (4)
- 2011年6月 (4)
- 2011年5月 (5)
- 2011年4月 (4)
- 2011年3月 (5)
- 2011年2月 (1)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |