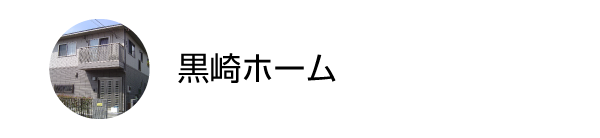日記
- HOME
- 施設長・課長日記
施設長・課長日記
波多江式インディアン的福祉論㉘(湘南セシリア・みらい社・湘南ジョイフル 施設長 波多江努)
4月より、湘南セシリア、みらい社、湘南ジョイフルの施設長となりました。
よろしくお願いいたします。
新年度に伴い、今年の抱負とも思いましたが、
今回もあえて、いつものごとくインディアンの言葉をご紹介いたします。
「土地は先祖からの授かりものではなく、子どもたちからの預かりもの。」
「どんなことも7世代先まで考えて決めなければならない。」
部族不明の2つの言葉です。
「土地」を「福祉(施策、諸計画、施設建物など)」と置き換えてみたり
「子ども」だけでなく、「利用者・家族、障害のある人」を加えてみたら、受け止め方はかなり広がってくる。
また、1世代を30年と捉えると約200年先。
具体的に200年としなくとも
5年・10年先や将来と捉えたとしても
今だけでなく、この先の福祉のあり方がどうあるべきなのか。
これまでの過去に敬意を払いつつ、未来を作っていかなければならないのだろうと思う。
残念ながら今の自分には、そんな難しいことはできない。
精一杯頑張りながらできそうなことは
いつまでたっても変わらない「普遍的な価値観」を見つけること。
自分が新人だった頃、先輩・上司から何を学び
一人前になってから大切にしてきたことは何なのか
上司となった今、何を託したいのか
何十年もかけながら自分たちは誰に何を伝えようとしているのだろうか。
技術や知識だけではない、今、この日記では言葉にはしきれない「大切な何か」があるような気がしている。
「(将来の夢)インディアンになる」にはもっと修業が必要ですね...。
我が家に飾ってある覆面レスラーキーホルダー。
難しいことを考えると、モノづくりがしたくなります笑。
ヤンソンさんの誘惑(法人事務局 課長 佐藤和美)
今年は、暖冬と言われつつも寒い日が多かったです。先日もとにかく寒くて買い物にも出かけたくない!家にある食材で作れるものないかな...と、スマホでレシピ検索をしていました。
『じゃがいも 玉ねぎ 簡単 レシピ』と検索すると、"ヤンソンさんの誘惑"の文字が目に入ってきました。一瞬、レシピ検索してたはず...と自分を疑いました。
"誘惑"とは、"惑う"の言葉がつくように、どちらかといえばネガティブな意味が含まれる言葉です。
惑わすの意味が含まれるため、"甘いものの誘惑に負けない"など相手を悪い方向に導くようなニュアンスがあります。負の意味を感じさせる料理名をどうして付けたのだろう?と興味が深まります。
マルゲリータ、サンドイッチ、八つ橋など、人の名前がついている料理名はあるけれど、修飾語として名前が入っている料理は、人生を半分過ぎましたが、初めての料理名です。
昔、スウェーデンの菜食主義者の宗教家エリック・ヤンソンさんが、この料理の香りと見た目に誘惑され、思わず食べてしまったというところから名付けられたそうです(諸説あり)。スウェーデンではクリスマス料理としても一般的で、日本では数年前のドラマで紹介され広まったようです。
玉ねぎは薄切りに、じゃがいもはせんぎりに、アンチョビはあらみじんに切ります。フライパンにバターを溶かし、玉ねぎ、ジャガイモも炒めたものとアンチョビをかさねて、生クリームとパン粉、バター、粉チーズをふりかけオーブンで焼きます。
オーブンから出した熱々を一口食べると、おいしい!寒い日にぴったりでからだが温まります。"誘惑"という負のイメージの料理名に疑惑を抱いていましたが、なるほどと思いました。
自分の中で常識と思っていることも、言葉通りと素通りせずに、確認することが大切なんだなと実感しました。
カロリー的には高めなので、"誘惑"の意味は間違っていなかったかもしれません。
※写真は日本で初めて発見さた恐竜の化石「フタバスズキリュウ」です
「球春到来」(サービスセンターぱる 課長 飯原佑)

早いもので、2024年度もあとわずかで、新年度に向けての準備を行っている時期になります。
忙しさや次年度への期待感を持ちながら、私としては野球シーズンへの高揚感がある時期にもなっています。
今年は、日本でメジャーリーグの開幕戦があり、その10日後には日本のプロ野球も開幕となります!
私は生粋の横浜DeNAベイスターズファンですが、今回のメジャーリーグの開幕戦で先発投手として投げる予定で、元ベイスターズ選手だった今永昇太投手がいます。
この選手はユーモア溢れる選手でいながら、自身の思考や投球に対する理論を言語化することに長けていることから「投げる哲学者」とも言われています。
そこで、私が心に残った言葉を紹介したいと思います。
「悪い試合こそ、あえて良いところを見つけて好投したときほど悪いところを見つける」
これはルーキーとして過ごした1年間を振り返るインタビューで話していた言葉です。
当時の日本を代表する投手と投げ合い、勝てなかった試合中にも、何がダメでそれは直せそうなのかを考えながら投げていたそうです。
整理をして落ち着き、客観的に自分を見ることも大事だと話していました。
この言葉に改めて気付かされたと同時に「そうは言っても難しいな...」と感じたことを覚えています。
どうしても悪いときには良いところに、良いときには悪いところに目は向かないものですが、今永選手の言葉を胸に、落ち着いて客観的な振り返りをしていきます。
写真は、春を迎える前に行った雪山です。
立川シティハーフマラソンでのボランティア(法人事務局・サービスセンターぱる 所長 石川歩)

先日、立川シティハーフマラソン2025にボランティアとして参加しました。
息子が所属するミニバスケットボールチームのメンバー達が出場する関係でお声がけいただき、昭和記念公園内のコース脇で観戦者の案内や交通規制のお手伝いをしました。
「ハーフマラソン」と名称にありますが、ハーフマラソンの他に10㎞や3㎞のレース、小学生が走る1マイル(1.6㎞)レース、親子ペアの部など、様々な距離や参加差に分かれて競技が行われます。
市民ランナーが参加する大会を想像してボランティアに行ったのですが、箱根駅伝の予選会のコースと一部同じコースなのもあり、ハーフマラソンは大学や社会人で陸上競技をされている方々が大勢参加されており、優勝タイムも1時間2分台と非常に迫力のあるスピード、競り合いが見られるレースでした。
私の持ち場はフィニッシュ地点から300メートルほど手前でしたが、観戦する方もそれほど多くなく、楽な気持ちのままでボランティアさせていただきました。
トップの集団が通り過ぎてからも、一般参加の方が多数走ってこられました。みなさんご自分のペースで思い思いに楽しんで走られている様子を見て、高校の頃に陸上部だった私も「久しぶりに走ってみたい」と感じさせられました。
もしかしたら来年は出場する・・・かもしれません。
「そういえば、、、」ふと思った事 (みらい社・湘南ジョイフル課長 石川大助)

最近、家に辞書がないことに気づいた。
いつまで在ったのか、思い出せない、、、。
思い出せないが、スマホやパソコンがあれば事が済んでしまうので、使わなくなったから?もっと前なのか?
昔は、分からない言葉を調べるのに、分厚い辞書を取り出してはぺらぺらとめくって調べていた。また、自分の目的に合わせて国語辞書、和英・英和辞書など何冊かもっていた。調べ始めその言葉を見つけると、あったあった!と嬉しくなり、もっと早く引けるようになりたいと子供のころに思ったのを覚えている。半面、目的の言葉にたどり着くまでに、いくつもの目的以外の言葉が視界に入り、なるほど、、、と目的から外れて別な言葉を調べ始めたりしてより時間を費やすことになったことも。辞書独特の紙の質感やめくる音も妙に好きだった。
今は、インターネットですぐに調べられ時間も手間もかからない便利さがあり、私もすっかり「調べる=インターネット」の思考になっている。コピーペーストや音声でも調べられたりする手軽さもあり、読めない言葉もコピーペーストで検索ができて何冊も辞書を持ち運ぶこともない。
今やインターネットが使えなくなったらと考えると困ってしまうほど当たり前なものとなっている。デジタルなものは何かと便利だが、アナログ感覚も大事にしながら、時にはデジタルデトックスを取り入れて、心身のケアやストレスを軽減してデジタルに馴染んでいこうと思う。
※写真はみらい社の2階から撮影した富士山
「ヒヤリハット」(湘南セシリア 課長 鈴木保志)

最近、視力の低下が気になる。12月の健康診断の視力検査の結果も、昨年度と比較するとかなり落ちていた。その他の検査結果が良くないのは心得ているが、視力検査では「右、左」と迷いなくクリアしていくことに若干の誇らしさを感じていたのだが、見えにくいとこれほどにも足掻くものなのか。目を細めたり「右・・いや下かな・・」と看護師の反応に探りを入れてしまう。
つい先日の出来事だが、週末の賑わうスーパーに妻と買い物に出かけた。物価高騰で野菜一つ購入するにも悩むところだが、比較的安いほうれん草が目に付く。妻のもとに駆け寄り「ほうれん草買う?」と顔を近づけると、見覚えのない顔。至近距離の為、あまりの恥ずかしさに「ごめんなさい!」と手を合わせると、相手の方が「大丈夫ですよ!」と爆笑している。頭を下げそそくさとその場を離れ、再接触を避けるべく一定の距離を取りお菓子コーナーへ。お菓子を手に取り妻のもとに駆け寄りカートに入れようとした刹那、見覚えのない顔。カートに入れかけた腕を引っ込め、何かにとりつかれたようにその場を離れる。2度も立て続けに・・! 故意であれば相当な悪趣味である。
確かに視力の低下を感じるが、今回の件は視力の問題なのか、判別機能の衰えなのか、総じて老化なのか・・いずれにせよ自身の油断と確認不足が招いた「ヒヤリハット」は、恥ずかしさも相まり胸のざわつく帰路となった。