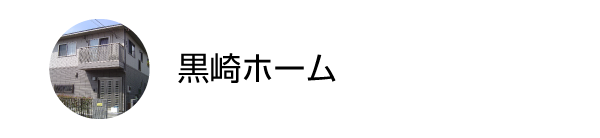日記
- HOME
- 施設長・課長日記
施設長・課長日記
『新年早々』(湘南だいち 課長 大澤 健二)

皆さん、年末年始はどんな過ごしかたをされましたか?私の場合、久しぶりに体調を崩し横になる時間が多かったような気がします。
年が明け、医療機関も再開したころ、体調不良がもっとも酷く、内科に受診をしたのですが、新型コロナウイルスやインフルエンザ、肺炎の検査などおこないましたが、何も原因がわかりませんでした。
医師とのやり取りの中で「ただの風邪【かぜ】ですかね?」と問いかけると、医師より「ただの風邪というものは無い」と言われました。続けて、「風邪とはどう漢字でかくか?」と投げかけられ、私は「風【かぜ】に邪魔【じゃま】の邪【じゃ】」と応えると、医師より「風邪という言葉の風しか読んでいないよね?」「それでは、邪魔の邪はなぜ読まないのか?」と、更に問いかけられた私はポカンとしてしまいました。
医師曰く、「風邪【かぜ】は【ふうじゃ】とも読み、今のように医学が発展していなかった頃、名前のつかない病に対し【ふうじゃ】と呼んでいた。だから、風邪【かぜ】などという名の病は無い。」と、新年早々、説法のような教えと薬をいただきました。
では、支援の話につなげて考えた場合どうでしょうか。
私たちが日常使う言葉や利用者が発信する言葉。普段、何気なく気に留める事の無い『言葉』を気に留めてみて下さい。実にそれは面白く、それ自体を理解する事で「言葉」の成り立ちや重みに触れる事ができ、自身の成長の糧となるのではないでしょうか。
そんな事を「新年早々」感じ考え、私は過ごしていました。
本年も宜しくお願いします。
「里帰り」(湘南ゆうき村・湘南だいち 施設長 妹尾 貢)

お正月は実家のある練馬に帰省しました。
実家は団地なのですが、この5年ほどの間に建て替えがあり、実家の場所も数年ごとに変わりました。今回は元の場所の新しい建物への帰省でしたが、自分が子ども時代を過ごした時の様子とは似ても似つかない、おニューな感じのマンション風になっていました。
それでも場所が同じなので、帰った感じがするのは不思議です。
障害福祉の世界では「地域の生活」「地域移行」など、地域という言葉をよく使います。地域って何だろうとよく考えます。すぐに思いつくのは「施設の反対語」なのですが、では「施設」の生活と「地域」の生活の質的な違いとは、なんだろうかと考えます。
自分が実家にいたころ、地域の活動を意識することは、あまりありませんでした。今思えば、団地の自治会で、階段掃除の日があったり、夏のお祭りがあったりしました。目の前が学校だったので、学校のイベントはよく行きました。
働き始めてからは藤沢に住みましたが、仕事ばかりで、地域の活動に参加することはほとんどありませんでした。一度、たまたま夏に帰省した時に夏まつりがあって、屋台で焼き鳥を焼いたことがあったくらいです。
ITの発展で、人と人をつなぐ仕組みは加速度的に変化して、端末さえあれば、足を運んだり人を介したりせずに、世界中の人とつながったり、いろいろなことが出来るようになりました。地元に帰らなくても、あちこちに散らばって住んでいる高校の同級生たちと、LINEで無駄話をすることもできます。
そうやって空間を超えてつながるようになっても、同じ土地にすむ「地縁」の関係もまた、続いていきます。
最近は、職場がある西俣野上町内会の住民活動におじゃますることがあります。自分の生まれ育った地域ではありませんが、住んでいる人たちのいろいろな課題を見聞きすると、なにか自分たちにできることはないか、と考えます。
そんな経験を通して、「人が役割をもって、直接にやり取りする距離感」それが地域かと考えました。施設に住んでいても、住民としての役割があれば、それは地域の暮らし、なのかもしれません。
その場所で暮らしたり働いたりする人として、役割をもつこと、役割があると実感すること、それを支援することが我々の仕事なのではないか、とあらためて思いました。
※写真は、子どものころ遊んだ近所の公園
~虫川大スギ~(相談支援プラザ 課長 一戸香織)

先日 帰省の際 大杉に会いに行きました。
大杉は樹齢1200年以上、高さ約30メートル。
周囲10.6メートルの全国的にも有名な巨木です。
当地では御神木とされており、昭和12年には文部省(現在の文部科学省)により、国の天然記念物に指定されています。
実家から近くにあるにもかかわらず、長い間会いに行く機会がありませんでした。
初めて大杉に会ったのは小学1年生の時の遠足でした。
大きな杉の木をクラスメートと手をつないで囲んだことや、
みんなでお弁当を食べ、話をしてたくさん笑った思い出が残っています。
久しぶりに会った大杉は、夏の強い陽ざしや冬の厳しい風雪に耐えて、凜としたその姿は生命力に満ちて私の前に立っていました。
しばらくその場から離れることが出来ませんでした。
誰もが将来の不安や日々の悩みを持ちながら生活を送っていると思います。
私は大杉から「大丈夫だよ」「気にしなくていいよ」「いつもあかるくね」と背中を押された気がしました。また大杉に会いにいきます。
そのとき私はどのような人生を送っているでしょう・・・。
2024年8月撮影
「新年」(よし介工芸館・アートスペースわかくさ課長 石田 友基)
新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
よし介工芸館・アートスペースわかくさでは、年明けに利用者さんと書初めをすることが恒例となっており、今年も皆さん想いを書いていました。
ふと、「書初め」について気になり、調べてみました。
書初めの意味としては
・字が上手になるように願う
・一年の目標や決意を決める
・心を新たにする
・やる気を持って行動を始められる
などの意味があるそうです。(AIによる概要 引用)
何気なく抱負や願いを書いていましたが、こうやって意味を知ってから取り組むとまた違った心持ちで字を綴れるようなきがします。
個人的には今年は前厄であり、去年から徐々に健康に不調をきたすことが増えてきたので、「健康第一」な年にしていきたいと思います。
半径5m(相談支援プラザ・よし介工芸館・アートスペースわかくさ 施設長 小野田智司)
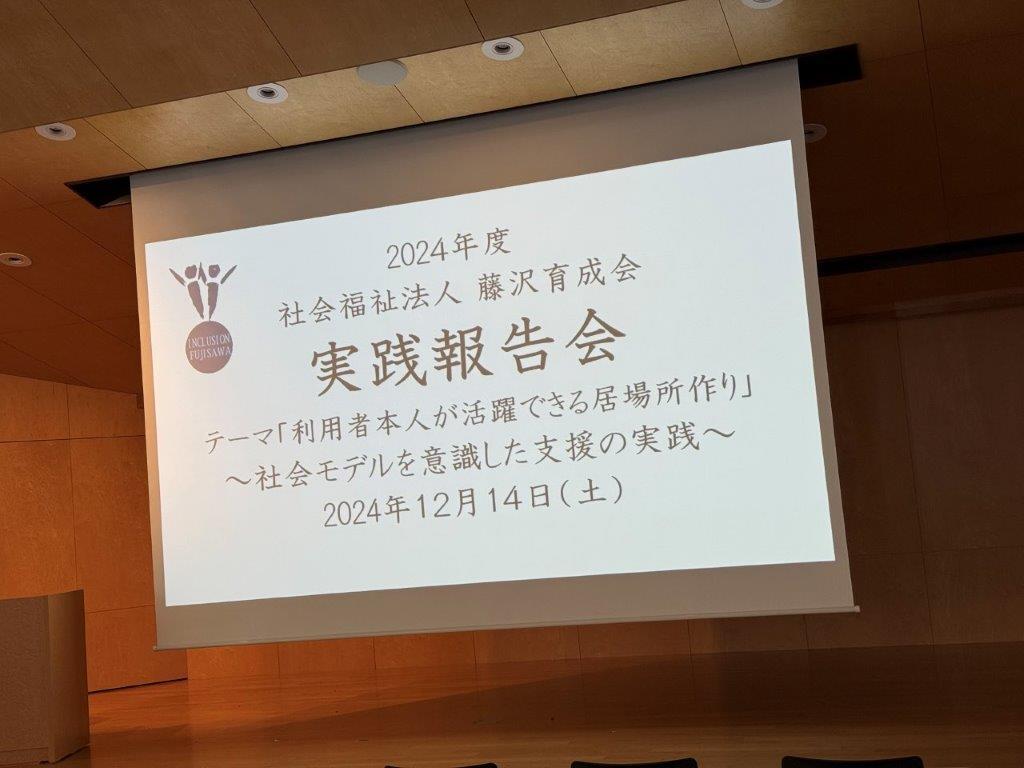
2025年になりました。
本年もよろしくどうぞお願いいたします。
2024年度母校で開催された
公開講座に複数回参加しました。
卒業生だけでなく、一般の方も含めての講座です。
教授より、問題提起がなされたのちに
参加者がそれぞれ今の自分のことを話し、
参加者の皆で応じるように意見交換し
深く考える場となりました。
私は「半径5m」の話をしました。
いろいろな支援計画書や
いろいろな会議は大事だけれども
やはり大事なのは、その「人」の日常の様子です。
「半径5m」
触れられそうで触れられない距離。
少し広そうですが、その方の様子はよくわかる距離。
ちょっとした雑談、
ちょっとした行動、
その範囲のなかの職員さんや環境、
その「ちょっとした」ことが
半径5mをみることで見えてきます。
ほかの参加者からは
能登半島地震および豪雨災害への対応について
ただボランティアとして泥をかき出したり
物を運んだりするのではなく、
住まう人の想いに寄り添いつつ
何気ないお話をすることのほうが求められている
けれど、ずっとはいられない...
など苦悩していることを共有がありました。
ほかにも
津久井やまゆり事件の話、
成長に心配する子育ての話、
とある施設での話、
様々な話の共有がありましたが
多くの共有点は
やはりその人の想いを基本に考えるということでした。
「半径5m」
皆様もちょっと意識してみてください。
■表紙の写真■
実践報告会
テーマ「利用者本人が活躍できる居場所作り」
~社会モデルを意識した支援の実践~
今年も盛りだくさんの内容で
写真や映像資料を示しながらの報告もあり
書面では気づけないことを
たくさん学ぶことができました。
日常から地域の方々との
継続的なつながりが
いかに大事か。
基本的な挨拶を継続します(^^♪
お城エキスポ(湘南あおぞら・アポロ 課長 髙橋羽苗)

チケットをいただきお城エキスポというイベントに行ってきました。
名前の通り、お城にまつわる展示や講演、ステージなどが一同に開催されるイベントです。
歴史的なものに興味はあるけれども詳しくはない私は、普段の観光でも「近くにお城があれば行ってみようかな」というほどで、わからないことがほとんど。イベントでも専門的(?)な言葉はわからないこともあり、いくつかの説明はいかにもわかったようなふりをして聞いてきました。
イベントの参加者は年齢層も幅広く、出展者と専門的な知識(?)で語り合っている方や、 家族で参加している方、歴史上の人物の衣装を楽しんでいる方など、会場はみんな思い思いに楽しめる雰囲気。
こういったイベントに行ってみると自分の趣味と言えるものが答えられない私としては、趣味や好きなことを楽しめる人たちを羨ましく感じます。あのパワーはやっぱりすごい。
そんなパワーに最初は圧倒されましたが、共通の興味を持ちながらも各々の楽しみ方で過ごしている空間はとても印象的でした。
イベントの一つに観光情報のエリアがあり、お城や武将、街の魅力などがPRされていて、私も気になるお城を発見。私も次の楽しみのきっかけをみつけたので、いつか行ってみようと思います。
▲かなり前に行った彦根城