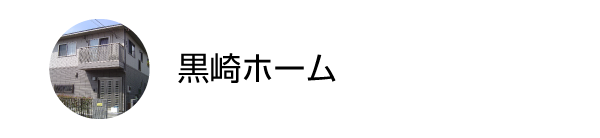日記
- HOME
- 施設長・課長日記
施設長・課長日記
「バレンティーノロッシ」(相談支援プラザ / 所長 伏見康一)

最近、仕事でバイクに乗るようになった。駐車や渋滞の難を避けられるので重宝している。
実はこれまでバイク運転はしたことがなかった。専用免許もないので乗れるのはバイクといっても原付のみ。そんな私だが、バイクレースを見るのは昔から好きだった。
今から30年くらい前、日本人ライダーが世界を席巻し、活躍する姿を見ていた。だがその並居る日本人ライダー達を颯爽と追い抜く怪童が現れた。その怪童の名はバレンティーノロッシ。現在「生きる伝説」と称されるロッシだが、10代で登場するやその速さと強さは突出しており憎らしいほど強い存在だった。瞬く間に世界チャンピオンとなり、絶対王者として君臨し続けた。
ロッシは「ノリック」ファンを高言していた。「ノリック」とはライダー故阿部典史の通称である。日本人ライダーの中でも唯一無二な存在だったノリックだが突然に夭逝してしまう。ノリックの死後ロッシは自車に「ロッシふみ」(ロッシ+のりふみ)と記しノリックのスプリットを継承したのだった。「憎き存在」から「尊ぶ存在」に、いつの間にか自分の想いもロッシに投影していた。
そのロッシが今年で引退することとなった。ここ数年の実績からすると避けられない現実かもしれない。飛びぬけてベテラン層であることに加え、若手の台頭、度重なるルール改訂、ダメ押しはコロナ禍のレース事情だった。ただ底抜けにバイクを愛し、常に闘争心ある雄姿が見られなくなるのは寂しい。残りあと数レースをしっかりと見届けたい。
私が出来ることは安全運転に徹し、どなたにも迷惑をかけないこと。バイクという存在に感謝をしながらグリップを握りたいと思っている。
*写真はトップ3(当時)と後方に写り込む拙姿。
第53回『言葉はコミュニケーションにとって万能の道具か?』

孫引きになるが、生物学者のマーク・パーゲルによれば「世界中で最も多くの言語を抱える地域は、人口密度の高い地域」と言うことである。
「パプアニューギニアに行くと、一つの島の中で八〇〇から一〇〇〇という数の異なる自然言語を見つけることができます。~中略~どうやら言語の使用目的は、協力だけにとどまらず、集団の輪を作り出したり、アイデンティティの確立と自分たちの情報・知枝・技術の盗用保護をしたりと多岐にわたります。」とも言っている。
人口密度が高くなると言語の数が増えるというのは、単一言語圏に暮らす我々にとっては矛盾することのように感じる。どうやら言葉というものは情報の伝達に役立っているだけではないと言うことがわかる。
外国人と仲良くなりたいと思ってその国の言葉を学ぶ気持ちと、一つの共同体(集団)が形成されると逆に村八分と言う排除の論理が働いて、そこから言葉が細分化するように働くと言うのは、よく考えてみれば言語の方には罪はなくて人の心の方に問題があるのだろう。
そう言えば、専門用語や業界用語というのもその特定の業種でしか通じないし、若者の言葉などは今の私には聞いていてもさっぱりわからない。言葉はコミュニケーションを良くする手段だけに使われるのではなくそれを阻害する働きもあると言うことらしい。
人間というものが、相当、厄介な生き物に思えて来た。
映像の温度 (湘南ゆうき村 課長 高橋 羽苗)
今年度の「いんくるウィーク」の企画として、地域の方やお世話になっている方々にも動画出演のご協力をお願いしています。
各事業所でお世話になっている方の撮影をさせていただくのですが、技術がないので、とても難しい...。コロナ禍で動画を使う機会は増えましたが、私自身慣れないこともあり、これまではその場にいてもなんとなく居心地の悪さを感じていました。
それでも今回の撮影は、ご出演いただく方にも楽しんでもらえるよう一緒に楽しむ!そしてその雰囲気を伝えることを目標に...。
慣れない撮影者ではありますが、それでも一緒に同じ時間を共有すると、出演していただく側も周りの方も一緒に盛り上げてくださり、皆さんのとってもいい表情を撮らせていただけているように思います。
動画の依頼やチェックをしていると、たくさんの方のお力で私たちの日々が成り立っているんだなぁと改めてつながりを感じられる機会となりました。
「課長日記」 (サービスセンターぱる 支援課長 鈴木 保志)
法人広報委員会から課長日記の掲載依頼案内があり、もうそんな時期?と驚く。いつもそうだ、他の業務同様に仕事の意識、段取りに問題があることは言うまでもない。
さて、何を書こうかと毎回部屋の中を眺め、視界に入るものからイメージを膨らませている。これも意識、段取りに問題ありか。「さて書くぞ、何を書くか・・」と酒の肴に考え始めると、もうどうでもよくなってくる。
文章がとても苦手だった小学生の頃(今もそうだが・・)、父親が私の読書感想文を読み「あらすじ」は感想文ではないことを指摘していたことを覚えている。何を言っているのか当時は分からなかったが、確かにあらすじを書いていた。「感想」ではなく「あらすじ」の為、読むと本の内容が大方理解できる。指定の文字数に到達出来そうにない時、終盤は詳細が記されたあらすじとなる。
日記、作文、論文、感想文・・さまざまあるが、そもそもこの文章は日記として成立しているのか?この機会に整理しておこうと思う。
『健康第一!』は、本当に大事だった。 (みらい社 課長 大澤 健二)

夏も終わり、秋の気配が少しずつ感じられる夕暮れ。
今回、健康の大切さについて痛感し、生活習慣の見直しと改善を図り始めた話を書きます。
(それ程の年齢ではないのですが)まだ若いと思っている日々。新年を迎えた頃、体調に変化が・・・。
近所の病院に受診したところ、紹介状を受け取る事に。
総合病院で検査。3つの科を受診すると、どうやら健康ではない事が判明。
医師より、色々と今後の事、治療やら服薬やらの説明を受ける中、この機会に「健康体質になりたい!」という思いが生まれてきました。そもそも、健康は、大きな負担やケガ、事故などに気を付けていれば大丈夫と言った無知な考えで生活していた私。
検査結果や医師の話を聞く中、そろそろそれも、そうでは無い世代に入ったのだと自覚しました。
まず、生活習慣で改めたのが睡眠前の食事と飲酒。
毎日、人に話すと驚かれる量で飲んでいたビールなどは一切飲まなくなり、同時に、夕(夜)食の好物の米や米料理、ラーメンなど炭水化物の摂取も控えめに。「チャーハン大盛!」「チャーシュー麺大盛!濃い硬で!」というオーダーを当たり前にしていましたが、もちろん今では大盛注文はしない。夕食の炭水化物は、時々食べる程度で、20時以降の食事は、食べないか野菜だけにする。
飲酒、夕(夜)食の炭水化物の喫食を控える事を続け、野菜とカニカマを中心とした食事を続けた結果、なんと!20代30代前半に穿いていたズボン、着ていた洋服が余裕を持って着用できる体型に。
目には見えない体内を休ませる事も意識し、働き方、睡眠時間も改善。慢性的な疲労感は殆ど無くなり、活力が徐々に戻って来ているのを感じる今日このごろ。
次に取組むのは、喫煙の卒業と定期的な運動の機会をつくる事。健康であるための生活習慣改善を続けていきます。
健康でない状態の不便さを味わった事は、「健康第一!」の言葉が深く腑に落ち体調の変化がきっかけで私は生活習慣の改善を取組み始めましたが、もしも、みなさんの中で、いずれ改善しようかな・・・と思う方がいらしたら、是非、今日からできる事から取組んでみて下さい。きっと、良い何かが得られるのではないでしょうか。
『虹って何色ありますか?』 (湘南あおぞら 課長 石川 大助)
8月の雨上がりの朝、出勤のため自宅を出て住宅街を過ぎた辺りで空に虹がかかっているのに気づいた。それだけで嬉しくなりますが、よく見ると薄っすらともう一本かかっていて、なんと二重の虹でした。テンション上がって写真を家族にメール!
雨上がりではあるも、晴れているわけではないのにと思いまながらも、なんとも幸運を感じる朝でした。
その後、ちょっとスマホで二重の虹について検索してみると、虹にはいくつか種類がある事が分かりました。
主虹(一般的な虹)
副虹(二重に掛かる虹)
過剰虹(内側に繰り返すように色が見える虹)
反射光虹(水面等に反射した太陽の光が、再び雨粒に反射されてできた虹)
霧虹(太陽の光が霧に反射して見える虹)
月虹(夜に月の光で生じる虹)
水平虹(太陽の下の薄雲の一部に出来る虹)
夜に虹が見えることがあるなんて、なんとも幻想的な虹まであるのだと知りました。
日本人は『虹って何色(なんしょく)ありますか?』と聞けば「7色」と答えますが、ドイツでは5色、他にも8色、2色と答える国もあるようです。微妙な色を表現する言葉があるかないかによって違いがでるようです。さらには、見る側が虹を「何色と見ようとするか」によっても違うそうです。
言われてみれば、、、。小さい頃から虹は7色と耳にして、その色の分け方の概念が当たり前なので7色に見ようとしていますし、そうとしか思えません。画像を見ても7色のグラデーションの境を探すように色を数えてしまいます。
もし、自分が他の国で育ったら『3色です』『5色!』と当たり前に言っているかもしれないと思うと、育つ環境によってとらえ方がつくられているのだと改めて感じました。
余談ですが、虹を見て以来、通勤時に空を見上げる事が多くなりました。建物の上に広がる毎日違う空模様に魅かれてしまいます。