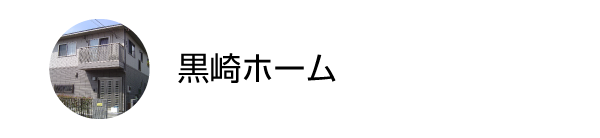日記
みらい社の施設長・課長日記
「春よこい」 ( 湘南セシリア・みらい社 / 施設長 石塚 和美 )

2月に入り、メジロの姿を見かけるようになりました。夕方も少しずつ日が長くなってきていることを感じます。
年明け、10年ぶりに母が我が家にやってきた。1週間滞在。
家の環境は昔のまま。遅ればせながらの大掃除で急きょ環境設定。風呂の脱衣場に温風ヒーター、洗面所・ベットの足元にマット設置、リビングにホカホカカーペット準備。段差の確認。
10年の間に家のまわりの環境がだいぶ変わった。店が変わり家並みが変わった。
私が休みの日に一緒に近隣の散歩。子どもが小さいときはよく手伝いに来てくれていたので顔見知りのご近所さんもいて安心だけれど環境の変化はなかなか難しい。
ウイークデイ、私が仕事の日、母はひたすら家事。食器棚、冷蔵庫内の整理、風呂場、リビングの清掃。帰宅するたび、家の中がきれいになっていく。以心伝心。ここをきれいにしたいという思いは母にはしっかり伝わっていた。
今まで来られなかった分、今後も定期的に母に来てもらうことになった。今度来るときは一緒に桜の花の下を散歩したいと思う。
103歳で逝った祖母は、寝たきりになっても「気をつけて帰りなさい」と気遣ってくれた。
仕事に追われ、自宅と仕事場の往復。母が来てくれ、どこかで誰かが見守ってくれていることを感じた時間でした。
散歩道。蝋梅の香りがしている。春はそこまで来ている。春よこい♪早くこい♪
『お言葉をいただいておもう』 ( みらい社 / 課長 大澤 健二 )

さて、「むじょう」という言葉から、みなさん何を想像しますか?
先日、ある方から「むじょう」について、お話をいただきました。
「無上・無情・無常」と無の次の漢字が一文字違う事で意味が変わります。もちろん、他にも同じように、一文字違いで意味や用途の変わる漢字や言葉は多くありますが。
私がいただいた言葉は、「無常」でした。
「命は儚いものである。あたり前は"つね"ではないからこそ、今は尊いもの。」
重みのある言葉でした。
無常を深く意識し、言葉の意味合いを理解しようとすると、社会福祉法人 藤沢育成会が取り組む "あたりまえの日常を見直す"は、とても重要であり、私個人で捉えた時、成長していくためにも努めて励む行動だということを改めて認識する機会となり、日常をただただ過ごすのではなく、見えるもの見えないもの、ひとつひとつの行動や景色、出来事などに心を留め考えらえるよう精進していきたいと思いました。
みなさんもぜひ一度、無常について言葉の意味に触れてみて下さい。
「アフターザレイン」 ( 湘南セシリア・みらい社 / 施設長 石塚 和美 )

コロナウイルスによる緊急事態宣言が9月末に解除となり特別措置法による時短要請も10月24日をもって解除となりました。
感染対策を行いながら、少しずつ元の生活に戻れるよう、このコロナ禍で得た新しい生活様式も取り入れながらこれからの季節を迎えたいと思います。
前回の施設長・課長日記を書いてから4か月。仕事や家事をする日常、家族や親しい仲間を想いながら過ごした日々。なかなか会えない中で、日々の電話やメール、ライン。そして手紙やはがきを出すことも増えました。以前よりも頻繁に連絡を取り合うようになった方々も多いのではないでしょうか。私も、数十年ぶりにいとこから電話があり、びっくりしたと同時に、連絡を取り合うことができるようになりうれしく思った出来事でした。
半面、体調不良時や、そばにいてあげたいときに、すぐに駆け付けることができずにもどかしく思うときもありました。
忙しくしているときには感じないさみしい気持ちやどうにもできない想いを、秋風がセンチメンタルな気持ちにさせます。これは「秋うつ」かなあと思いネットで調べたところ、「日光を浴びてセロトニンの分泌を促す生活を習慣づけましょう」とアドバイスがありました。
この頃は、週末も忙しくなかなか散歩もしていなかったと反省し、散歩を再開、秋風も心地よく感じるようになりました。これからは、自粛していたお寺巡りも御朱印帳を持って出掛けたいと、久しぶりに気持ちがワクワクしています。
お互いを案じながら、まずは自分が元気でいることが一番大事だと感じた秋の日でした。
写真は我が家の庭の数珠。そして家庭菜園にやってきたアゲハチョウの幼虫。彼らにもたくさん元気をもらいました。
「星に願いを」 (湘南セシリア・みらい社 施設長 石塚 和美)
2020年、コロナ禍で生活が一変しました。休校、外出の自粛。いつもと違う日常にとまどう1年でした。その中で、コロナ対策をしながら何ができるか。仕事でも、日常の生活でも「できない」ことより、「今この環境でできること」を考えて行動した一年だったと思います。
職場では、感染対策を徹底し、支援の中で利用者が楽しめる企画や、従来どおりの活動をどのようにしたらおこなえるか、工夫とアイデアを凝らし実行してきました。
私生活でも、大好きな音楽をいかに楽しむか。月に一度はライブへ行っていたあの頃。コロナの中で、イベントやライブ・演奏会が次々と中止となる中、演者もライブを楽しみにしていた人たちも不安な中で過ごしました。そして、「時間が過ぎるのを待つ」のではなく、「今、何ができるのか」。たくさんの演者が配信という方法で発信してくれました。あたり前だった音楽を聴くということが、新鮮で感謝の気持ちで聴く日々。音楽だけではなく、絵本の読み聞かせや詩の朗読なども、そこにはいないけれど同じ時間を共有している人たちがいることを感じる時間がもてました。
昨年から、自転車通勤となり、風や季節を感じることも多くなりました。この頃は、満月が時期により「スーパームーン」と呼ばれ、季節により呼び名も変わるくらい注目されています。流星群もよく報道されるようになりました。仕事の帰り道は、夜空を見ながら今日一日の反省や楽しかったころを思う時間でもあります。
この原稿を書いているのは7月7日。七夕。我が家には七夕飾りは飾っていませんが、空を見上げて願いを唱えました。七夕の日、あなたは何を願いましたか。
「パン工房 あゔにーる」はじまります(湘南セシリア、みらい社 /施設長 石塚 和美)
暖かな春の陽を感じながら、今年は例年よりも早い桜の開花となりました。
2020年度は、新型コロナウイルス感染予防対策を行いながら日常生活を送り、今年1月からの緊急事態宣言もようやく解除となり、ほっとした気持ちと同時に引き締まった思いで桜の花を見上げています。
藤沢育成会で唯一の就労支援事業所の「みらい社」。主に軽作業や施設外就労をおこなってきましたが、新しい作業としてパンの製造販売を始めることとなりました。一昨年度より計画していたパン工房。工賃アップや地域との繋がりを目的として、昨年よりパン製造販売事業を行うための具体的な販売計画をたててきました。1月よりみらい社の第2工場をパン工房にするための改修工事が始まり、3月中旬にオーブンなど機材の搬入も終わりました。4月のパン工房オープンにむけて、利用者・職員ともにパン作りの練習を行ってきました。

お店の名前は「パン工房 あゔにーる」。フランス語で「みらい」という意味です。新しい作業としてのパンづくりに取り組む利用者の真剣な顔、パンの焼きあがった時のうれしそうな顔。焼きたてのパンをたくさんの人に食べていただけるように、利用者・職員一丸となって取り組んでいきます。販売先は、みらい社、藤沢市役所分庁舎などです(詳しくはHP参照ください)。是非みなさんも焼きたてパンを買いに来てください。
『よもや よもやだ!』(みらい社 課長 大澤健二)

先日、ご高齢の男性を保護した。
その男性は、坂道のガードレールを伝いながら登っていた。
「●●時25分(たしか)、靴は履いている」と判断が迷う。
「外気温2度でジャンバー着ていない...」「散歩ではないな」。
近くの駐車場で方向転換。片側一車線の国道で、この時間でも車の量は多い。
私:「おじいさん、どこ行くの?」
じいさん:「もう歩けない」
私:「おじいさんさ、どこ行くのよ?」
じいさん:「ちょっと休むから、そこに座る」
私:「座る場所ないから、(壁)ここにつかまって」
おじいさんが壁につかまっている間に、警察へ連絡。
私:「高齢の男性を保護したので、パトカーで来て下さい。」
交換手:「住所はどの辺ですか?何歳ぐらいですか?」
私:「住所はわかりませんが、○○の交差点を△△方面に向かう途中の、タイヤショップがあって居酒屋があってバイク屋がある当たりの反対側歩道です。年齢はたぶん、80代後半だと思います。」
交換手:「わかりました。付近にいる警官を向かわせます。」
男性は長袖のシャツしか着ていなかった。
車からブランケットを出し、男性の肩を包んで上からジャンバーを掛け、歩道の生垣に座らせてもらいパトカーが来るのを待つ。
5,6分位して、2台のバイクで警官が到着。
パトカーではなかったが、早い到着で良かった。
警官①は若手で20代後半前、警官②は30代半ばくらいなのだろう。二人とも声も肌も若い感じがするが、明らかに警官②は先輩か上司なんだろう。
警官は、男性に色々質問するが、質問と答えは一致しない。当然だろう。
警官に家を聞かれた男性は、家を案内する事になってしまった。
「大丈夫かなぁ・・・」
男性に両手を前にしてもらい、私が両手で手を引く姿勢で移動する。男性はこの移動方法に慣れている様子で、腕への力の入れ具合は丁度良かった。
今まで保護してきた時の警官達の対応は、まずパトカーに乗せ2人のうち一人の警官が所在不明者の届がないかを署に問い合わせ、もう一人は要保護者の対応にあたるという連携。今回は様子が違う。
「そこが家だよ」「あれ、玄関がなくなっている」と、男性の言葉に合わせ「おじいさんこっち?こっちじゃないみたいだから、どこなの?」
「こっちだったけな」男性は案内を続ける。警察官はその通り家を探す。
15分位歩き、男性がいよいよ歩けなくなりマンションのエントランスに座り込んだ。
警官①:「おじいさん、ここは入口だからこんな所に座っちゃだめだよ。」
私:「おじいさん、ここ(エントランスの生垣)に座りましょうか」
警官②:「後は我々で対応しますので、お引き取りいただいて大丈夫ですよ。」
私:「ブランケットとジャンバーは、私の物をかけているんですが」
警官②:「持ち帰っていただいて大丈夫ですよ」
私:「いやいや、それじゃあ寒いでしょう」
警官②:「後はこちらに任せて大丈夫ですから、ありがとうございました。」
私:「たぶんトイレにしばらく行ってないと思うので対応して下さいね。よろしくお願いします。」
きっと大丈夫。
二人の警察官に後は任せ、その場を離れた。
「じいさん、大丈夫かなぁ。鼻水でてたしなぁ。」
心配ともやもや感の残る帰路。
われわれ福祉関係者は、対人援助職として、利用者、ご家族に『安心だね』や『大丈夫だね』を少しでも多く感じてもらえるような支援をしたいものだと思いました。