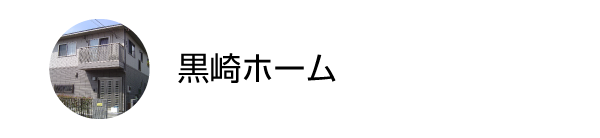日記
湘南ゆうき村の施設長・課長日記
なす(湘南ゆうき村・アポロ 課長 高橋 羽苗)

今年の夏は、湘南ゆうき村の畑でたくさんのなすを収穫しました。
なすの苗を植える時、「なすはうまくいけば長い時期でたくさん楽しめる」と教えていただいていたのですが、半信半疑でのスタート。それでも、9月までの収穫本数を振り返ると1200本以上のなすを収穫しました。
今年は、雨天が続き野菜が高騰したこともあり、100円で販売していたなすは超特価!利用者さん、職員をはじめ、湘南ゆうき村に来館された方にも大好評でした。
コロナウイルスの影響で、外出を控えていた中、畑活動は植物の強さと季節の変化を感じられる場所となりました。実がなりはじめたころには、まだ目線よりだいぶ低かった苗ですが、真夏の暑い時期には、反対側に立っている人が見えなくなるほどの大きさに。剪定では、どの枝を残すか、どの葉を落とすかと教わるものの思うようにはできず。。それでも、残した枝はすぐにぐぐっと伸びて、つやつやぱつぱつのはち切れそうな実が枝をぐっと垂らし、かごいっぱい収穫ができました。その頃には、活動としても定着して、利用者さんの収穫も切り取る箇所や収穫のサイズがだんだん揃ってきて、利用者さんから、「茄子とらないと!」と声がかかることも。涼しくなってきて、さすがに頻度は減っていますが、秋なすとして今も収穫が少しずつ続いています。
外での活動に制限があった今年の夏、できなかったこともたくさんありましたが、この夏だったからこそ盛り上がれた取り組みだったかなと思います。夏のカエルや、秋に支柱にとまるトンボも、数に「うっ...」と思いながらも季節がちゃんと動いていることを感じさせてくれました。
ご協力いただいた皆様ありがとうございました。
「令和の時代劇」(湘南ゆうき村/アポロ 施設長 三嶌 悟)
新型コロナウイルスの影響で遅れていた、テレビドラマ「半沢直樹」が始まった。心待ちにしていた人も多いことが、視聴率からも伺える。今回の「半沢直樹」は、2013年以来の続編となっている。
私も、2013年の第1弾を観ていた。その時は、「やられたらやり返す、倍返しだ」のインパクトさと、緻密な展開とテンポの良い展開にスカッとし心が躍った。
そして、続編である第2弾。めまぐるしく動く展開がスリリングで興味深い。「令和の時代劇」という所以にも納得できる。
しかしなぜか、第1弾と第2弾の時では、楽しさという気持ちに変わりはないが、第1弾の時より今回の第2弾は、やや複雑な心境を覚えてしまう。
それは、立場による視点の違いにあると感じた。第1弾の時は、現場の責任者として主人公の行動に胸が高鳴った。第2弾の今回は管理職として、対峙者や組織としての反対側の心境にも理解することができる部分もある。(自分に投げかけられているのかとも)
私の今年度のテーマは、「支援と事業の透明性」を掲げている。そういった意味では、主人公の「透明性」には大いに共感できる。
組織や事業は、人が動かすものである。少なくとも、自分自身が「倍返し」されないように、謙虚に邁進していきたい。
写真は、リニューアルした小会議室(相談室)です。オンライン会議にも対応しています。
日曜日の夕方(湘南ゆうき村・アポロ 課長 高橋 羽苗)
週末を自宅で過ごすようになり、日曜日の夕方にテレビを見ていることも慣れてきました。外にいることが多かった週末や、シフト制の勤務で、これまであまり実感を持っていなかった「サザエさん症候群」の感覚を持つことがあります。基本的にだらだらと週末を過ごしていることが多い私には、だらだらしていたい気分から「動く」ことの切替が苦手。
そんな時は、一週間の過ごし方を妄想しながら夕食を準備するようになりました。過ごし方は、好きなアイスを食べる事だったり、気になってる棚を掃除することだったりと様々。同時に一週間の予定も確認しますが、具体的に仕事を考えるのではなく、「今週はあれとあれと...」という程度。うまくいっていない仕事を思い出して「あぁ...」と気が重くなることもありますが、意外とふっとヒントを見つけられることも多く、「そっかそっか」と自分の中で納得できれば、私の「サザエさん症候群」は終了。自分の中でイメージが決まれば、その後はすっかり忘れてのんびり過ごします。
翌朝、職場に到着して、週末に残したメモに思いもかけなかった事柄を見つけて慌てることもありますが、ちょっとした気持ちの準備でウィークデーのリズムに戻ることができていることを感じます。妄想をすることで脳の活性化や、プラス思考になることがあると言われることもありますが、私の妄想は、切替のきっかけとして大切な時間となっています。
「意識を高めること・変えること」(湘南ゆうき村 アポロ 施設長・三嶌 悟)
2020年度がスタートしました。新型コロナウイルスの影響に伴い、世の中の動きや生活にも様々な変化が生じています。先の見えない状況には、自分たちの「意識を高める」、「意識を変える」ことが重要であると気づかされます。
先日、スーパーのトイレに入った時のことです。手洗いをして手を乾かそうとしたら、「エアータオル」が感染予防の一環として、使用中止となっていました。その時に感じたのは、どこまでの根拠があるかはわかりませんが、水分が飛び、空気中にウイルスが浮遊することを防止する為だと気づかされました。
上記は一つの例ではありますが、これまでの「エコや便利性等」は、公衆衛生上や感染予防の観点からでは、通用しないことも生じてきます。そうなると、どうしたら今の状況に適応していけるのか、意識を変えていかなければなりません。
「意識を変える」には、意識を高めなければ、気づきや発想は生まれません。また、「意識を高める」ことは、感染予防にも繋がります。
「意識を高めること・変えること」で、「連動や連携」にも関係してきます。そして、私たちの生活や仕事にも通じる部分です。
適切な情報を更新しながら、心と力を合わせて難局を乗り越えていきたいと思います。
湘南ゆうき村事務所のレイアウトを変更しました
声掛け (湘南ゆうき村 高橋羽苗)
新型ウイルスの流行の影響で、プロ野球のオープン戦が無観客試合として開催されました。観客の応援がない静かな環境の中で、ボールのキャッチの音、バットで打つ音などが聞こえると話題になっています。
私が「違い」を感じたのは、選手たちの声。普段から、ホームランやナイスプレーがあったときには、ベンチ席で喜んでいるチームの様子が見られますが、なかなか声までは聞き取れず、映像でも表情やジェスチャーなどで「喜んでますね」などと解説者が説明をしていたり、観戦に行ってもなかなか聞こえてはきません。
普段から、「お互いに声を掛け合って」「確認して」という言葉をよく使います。チームでの仕事の中で、確認や質問、共有のために声をかけあうことはありますが、選手たちの声掛けはそういったものだけではなく、士気を高めたり、一緒に喜ぶ声。時には相手のプレーを称賛している声。チームプレーの野球では当然のことなのかもしれませんが、チームで仕事をしていく中で、そういったことがなかなかできていないことに気づかされました。
新年度を迎え、また新しいチームとなっていきます。残り半月の今のチームと新しいチーム。チームでの「声掛け」を大切にしていきたいと思います。
写真:満員の横浜スタジアム。そうはいっても応援できる日が待ち遠しいです。
【波多江式インディアン的福祉論!? ⑪】(湘南ゆうき村 分場アポロ 波多江努)

北アメリカ南東部,アパラチア山脈南部に居住するチェロキー族には、約180年前、強制移住法により1000キロの移動を余儀なくされ、厳しい冬の寒さのために移動中に何千人もの死者がでたという深い悲しみの過去があります。(Trails of Tears:涙の道・涙の旅路)
そのチェロキー族の言葉に「過去を忘れ、心から痛みを消し去れ。どんな強い人間もそんな重荷に耐え続けることはできない。」という言葉があります。
私達にも忌々しい過去や受け入れがたい記憶、癒えることのない心の痛みがあり、その多くは忘れ、消し去る事が出来ないがゆえに大きな葛藤やコンプレックスとなっている方もおられるのでしょう。
しかし、あえて「忘れ、消し去る」と表現していることに覚悟や信念を感じます。
また、そのために自分に何ができるのか、何が必要なのかを考えるべきだと言われているようです。
実はチェロキー族には、その答えにつながるかのように「昨日のことで今日を消耗させてはならない。」という言葉もあるのです。
過去のことで未来を消耗させないような現在を過ごし、重荷に耐え続けるのではなく受け入れることが大切だと理解しています。
そして、過去や心の痛みを癒すことができるのは、これからの自分なのかもしれません。
「(将来の夢)インディアンになる」にはもっと修業が必要ですね...(笑)
画像...満ち足りた「今」を感じる私の癒しは、やっぱりモノづくりです‼