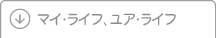東日本大震災の被災地の方たちのご苦労に、心からお見舞い申し上げます。今、日本人の誰もが、この未曾有の災厄に心を悼め、自らの気持ちと振る舞いの拠り所を求めているように思います。
震災後、すぐに思い浮かんだのは、やはり鴨長明の『方丈記』でした。鴨長明が生きたのは平安朝の末期から鎌倉時代の初期、源平の合戦を経て、日本史上初めての武家政権が成立する、政治t的にも社会的にもまさに乱世の時代でした。かてて加えて、飢饉、竜巻、大地震などの自然災害が鴨長明の住む京都にも容赦なく襲いかかってきていました。人の力では如何ともしがたい、自然の災厄を目の当たりにした鴨長明が、その有り様を心意の筆で描写し、無常観を謳い上げたのが『方丈記』です。
おそらく20数年ぶりに読み返した『方丈記』に次のような一節がありました。飢饉に苦しむ、京都の町を彷徨った後、鴨長明はこう記します。
いとあはれなる事も侍りき。さりがたき妻、をとこもちたるものは、その思ひまさりて深きもの、必ず先立ちて死ぬ。その故は、わが身は次にして、人をいたはしく思ふあいだに、まれまれ得たる食物をも、かれに譲るによりてなり。されば、親子あるものは、定まれる事にて、親ぞ先立ちける。又、母の命つきたるを知らずして、いとけなき子のなほ乳をすひつつ臥せるなどもありけり。
<小林私訳>
たいへん悲しく、胸のつまることもあった。離れがたいほど愛しあっている妻や夫をもっている人は、その思いがより深い方が必ず先に亡くなった。それは、自分のことは二の次にして、相手のことを大切に思うあまりに、何とか手にいれることの出来た食物もその人に譲ってしまうからだった。こうして、親子は、この世の決まり事のようにして、親の方が先に亡くなっていった。また、母親の命が尽きたのも知らずに、あどけない子どもが、乳を吸いながら添い寝を続けている姿なども見られた。
慈しみが深く、他人を思いやる人ほど、来世への道を急いでしまう。良き人ほど、帰っては来なかった。東日本大震災の犠牲者の方たちにも、たくさんの良き人たちがいました。自らは一度避難したのに、息子や娘を、妻や夫を、孫を、生徒を、もう一度救い直そうと難所に引き返し、そのまま行方を絶った人たちが、数多くいました。
救うべき人も救おうとした人も、永遠の無念に飲みこまれていきました。残された者は、涙を流す術もなく、瞑目するばかりです。
『方丈記』は、無常の書と言われます。愛する人への義務を自らの決断で静かに果たし、帰って来なかった良き人たち。私たち日本人の心の歴史には、こうした草莽の良き人たちの遺志が脈々と受け継がれています。その無念の遺志をこそ、長明は無常と言ったのかもしれませんが、その無常は、私たちに静謐でありながらとても大きな勇気を与えてくれる筈です。
写真・湘南あおぞらの庭がタンポポで満開になりました。

- 2019年12月 (1)
- 2019年11月 (4)
- 2019年10月 (5)
- 2019年9月 (4)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (5)
- 2019年6月 (4)
- 2019年5月 (4)
- 2019年4月 (5)
- 2019年3月 (4)
- 2019年2月 (4)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (4)
- 2018年11月 (4)
- 2018年10月 (5)
- 2018年9月 (4)
- 2018年8月 (4)
- 2018年7月 (5)
- 2018年6月 (4)
- 2018年5月 (5)
- 2018年4月 (4)
- 2018年3月 (4)
- 2018年2月 (4)
- 2018年1月 (5)
- 2017年12月 (4)
- 2017年11月 (4)
- 2017年10月 (5)
- 2017年9月 (4)
- 2017年8月 (5)
- 2017年7月 (4)
- 2017年6月 (4)
- 2017年5月 (5)
- 2017年4月 (3)
- 2017年3月 (5)
- 2017年2月 (2)
- 2017年1月 (2)
- 2016年12月 (3)
- 2016年11月 (2)
- 2016年10月 (2)
- 2016年9月 (2)
- 2016年8月 (3)
- 2016年7月 (4)
- 2016年6月 (4)
- 2016年5月 (5)
- 2016年4月 (4)
- 2016年3月 (5)
- 2016年2月 (4)
- 2016年1月 (4)
- 2015年12月 (4)
- 2015年11月 (4)
- 2015年10月 (4)
- 2015年9月 (5)
- 2015年8月 (4)
- 2015年7月 (4)
- 2015年6月 (5)
- 2015年5月 (4)
- 2015年4月 (4)
- 2015年3月 (5)
- 2015年2月 (4)
- 2015年1月 (4)
- 2014年12月 (4)
- 2014年11月 (4)
- 2014年10月 (4)
- 2014年9月 (5)
- 2014年8月 (4)
- 2014年7月 (4)
- 2014年6月 (5)
- 2014年5月 (4)
- 2014年4月 (5)
- 2014年3月 (4)
- 2014年2月 (4)
- 2014年1月 (4)
- 2013年12月 (4)
- 2013年11月 (4)
- 2013年10月 (5)
- 2013年9月 (4)
- 2013年8月 (4)
- 2013年7月 (5)
- 2013年6月 (4)
- 2013年5月 (4)
- 2013年4月 (5)
- 2013年3月 (4)
- 2013年2月 (4)
- 2013年1月 (4)
- 2012年12月 (4)
- 2012年11月 (4)
- 2012年10月 (5)
- 2012年9月 (4)
- 2012年8月 (4)
- 2012年7月 (5)
- 2012年6月 (4)
- 2012年5月 (5)
- 2012年4月 (4)
- 2012年3月 (4)
- 2012年2月 (4)
- 2012年1月 (4)
- 2011年12月 (4)
- 2011年11月 (5)
- 2011年10月 (4)
- 2011年9月 (4)
- 2011年8月 (5)
- 2011年7月 (4)
- 2011年6月 (4)
- 2011年5月 (5)
- 2011年4月 (4)
- 2011年3月 (5)
- 2011年2月 (1)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |