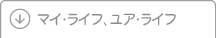日本でもハロウィンのお祭りが、年々盛んになってきている。10月に入ってから、あちこちでHalloweenの文字や例のかぼちゃの人形を見かけた。ここ数年の様子を見ているとハロウィンは、すでに一過性のブームを越えて、すっかり年中行事となってきているようだ。もちろん、お菓子業界やコンビニ業界のコマーシャリズムが、日本にハロウィンを定着させた原動力になっていることは間違いなかろう。でも、それだけでは説明しきれない、もっと深層の理由があるような気もする。ハロウィンは古代ケルト人の風習にその起源を持つという。ウィキペディアでは、こう解説されている。
ケルト人の1年の終りは10月31日で、この夜は夏の終わりを意味し、冬の始まりでもあり、死者の霊が家族を訪ねてくると信じられていたが、時期を同じくして出てくる有害な精霊や魔女から身を守るために仮面を被り、魔除けの焚き火を焚いていた。これに因み、31日の夜、カボチャ(アメリカ大陸の発見以前はカブが用いられた。スコットランドではカブの一種ルタバガを用いる[2]。)をくりぬいた中に蝋燭を立てて「ジャック・オー・ランタン(Jack-o'-lantern)」を作り、魔女やお化けに仮装した子供たちが近くの家を1軒ずつ訪ねては「トリック・オア・トリート(Trick or treat. 「お菓子をくれないと悪戯するよ」または「いたずらか、お菓子か」)」と唱える。家庭では、カボチャの菓子を作り、子供たちはもらったお菓子を持ち寄り、ハロウィン・パーティーを開いたりする。お菓子がもらえなかった場合は報復の悪戯をしてもよい。
9月の十五夜の晩、90歳になる母が玄関から外に出て、5分ほどして戻ってきた。
「十五夜のお月さんを眺めてきたよ」と言う。そして、母は秋田県の大館市の出身なのだが、問わず語りに田舎の十五夜の風習について話し始めた。母が小学生の頃の事だから、昭和10年代の話である。「戦争からあとは、田舎でもこんなことしなくなってるけどねえ」と言う。大館の村の、今は滅びてしまった十五夜の風習はこんな様子だった。
その年の秋に収穫したばかりの新米で作った団子と、これまた獲れたばかりの枝豆を茹でたものを縁側にお供えする。神様への収穫の感謝である。村中の家々の軒先に、美味しそうなご馳走が並ぶ。近所の男の子同志が集まって五人組を作る。この腕白坊主五人組が列を作って村を練り歩く。
「米あげたか、豆あげたか」
「米あげたか、豆あげたか」
家々の軒先で子どもたちが、大声で唱和する。縁側に並んだ団子や豆を、喜び勇んで子供たちが盗っていく。大人たちは団子や豆を、子どもたちが持っていきやすいように縁側の一番目立つ所に置いておく。美味しいご馳走にありついて、子どもたちは大はしゃぎする。五人組の子どもたちは再び列を作って道を練り歩き始める。次の一軒に着くと、また唱和する。
「米あげたか、豆あげたか」
「米あげたか、豆あげたか」
古代ケルト人の子どもたちと大館の子どもたちは、まったく同じように、大騒ぎし、遊び回りながら、秋の収穫物のご相伴に預かっている。時代と民族を越えた、習俗風習の相似性に驚かされる。ハロウィンと十五夜は、まったく同じ構造を持ったお祭りである。大人の労働と子どもの遊びと神への感謝。この3つが絶妙に組み合わさった、何とも楽しい秋の収穫祭なのである。
日本人がハロウィンを素直に受け入れ、あっと言う間に年中行事としてしまったのは、同じ農耕民族の血に由来するのではないかと思う。かつて日本の田舎にあった、十五夜のにぎやかな一夜への郷愁がハロウィンを流行らせているのではないか。そして、その郷愁の基層には、あどけなくもやんちゃな、子どもたちの遊び心がひそんでいる。

- 2019年12月 (1)
- 2019年11月 (4)
- 2019年10月 (5)
- 2019年9月 (4)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (5)
- 2019年6月 (4)
- 2019年5月 (4)
- 2019年4月 (5)
- 2019年3月 (4)
- 2019年2月 (4)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (4)
- 2018年11月 (4)
- 2018年10月 (5)
- 2018年9月 (4)
- 2018年8月 (4)
- 2018年7月 (5)
- 2018年6月 (4)
- 2018年5月 (5)
- 2018年4月 (4)
- 2018年3月 (4)
- 2018年2月 (4)
- 2018年1月 (5)
- 2017年12月 (4)
- 2017年11月 (4)
- 2017年10月 (5)
- 2017年9月 (4)
- 2017年8月 (5)
- 2017年7月 (4)
- 2017年6月 (4)
- 2017年5月 (5)
- 2017年4月 (3)
- 2017年3月 (5)
- 2017年2月 (2)
- 2017年1月 (2)
- 2016年12月 (3)
- 2016年11月 (2)
- 2016年10月 (2)
- 2016年9月 (2)
- 2016年8月 (3)
- 2016年7月 (4)
- 2016年6月 (4)
- 2016年5月 (5)
- 2016年4月 (4)
- 2016年3月 (5)
- 2016年2月 (4)
- 2016年1月 (4)
- 2015年12月 (4)
- 2015年11月 (4)
- 2015年10月 (4)
- 2015年9月 (5)
- 2015年8月 (4)
- 2015年7月 (4)
- 2015年6月 (5)
- 2015年5月 (4)
- 2015年4月 (4)
- 2015年3月 (5)
- 2015年2月 (4)
- 2015年1月 (4)
- 2014年12月 (4)
- 2014年11月 (4)
- 2014年10月 (4)
- 2014年9月 (5)
- 2014年8月 (4)
- 2014年7月 (4)
- 2014年6月 (5)
- 2014年5月 (4)
- 2014年4月 (5)
- 2014年3月 (4)
- 2014年2月 (4)
- 2014年1月 (4)
- 2013年12月 (4)
- 2013年11月 (4)
- 2013年10月 (5)
- 2013年9月 (4)
- 2013年8月 (4)
- 2013年7月 (5)
- 2013年6月 (4)
- 2013年5月 (4)
- 2013年4月 (5)
- 2013年3月 (4)
- 2013年2月 (4)
- 2013年1月 (4)
- 2012年12月 (4)
- 2012年11月 (4)
- 2012年10月 (5)
- 2012年9月 (4)
- 2012年8月 (4)
- 2012年7月 (5)
- 2012年6月 (4)
- 2012年5月 (5)
- 2012年4月 (4)
- 2012年3月 (4)
- 2012年2月 (4)
- 2012年1月 (4)
- 2011年12月 (4)
- 2011年11月 (5)
- 2011年10月 (4)
- 2011年9月 (4)
- 2011年8月 (5)
- 2011年7月 (4)
- 2011年6月 (4)
- 2011年5月 (5)
- 2011年4月 (4)
- 2011年3月 (5)
- 2011年2月 (1)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |