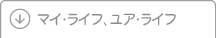最近、米原万里さんのエッセイを集中的に読んでいる。米原さんは、ロシア語同時通訳の第一人者として活躍し、日露の外交会談は米原さんの通訳なしには成り立たないとまで言われた人である。特にエリツィン元大統領には、「マリコ、マリコ」と寵愛に近い信頼を受けていたという。米原さんは2006年に56歳の若さで夭折してしまったが、『魔女の1ダース』、『嘘つきアーニャの真っ赤な真実』などの珠玉のエッセイ集を数多く残した。
その米原さんの最後の本が『打ちのめされるようなすごい本』である。がんとの壮絶な闘病生活を送りながら、週間文春に連載した「私の読書日記」などを収めた書評集である。この米原さんの書名の言葉を借りて、最近聞いた、「打ちのめされるようなすごい一言」を紹介したいと思う。
<精神科医は患者本人をナンバー・ワンとしてそのナンバー・ツーを務めるから向いていたのであろう>
(中井久夫『「昭和」を送る』あとがきより)
中井久夫は、今の日本で最も信頼のおける精神科医だと思うが、我々対人援助職に関わる者たちにも、数々の論文やエッセイを通じて、励ましと示唆を与えてくれている人である。その中井師のことばだからこそ、これは燻し銀千両の重みがある。患者本位とか本人中心とかということは、今やある意味スタンダード過ぎる理念で、誰でも口にする。だから、この言葉も駆け出しや凡百の精神科医の台詞だったら、鼻持ちならないエエカッコシイにしかならないだろう。私は精神科医ではないが、同じ対人援助職に就く身として、こういう言葉をさらりと何の衒いも気負いもなく言えるようになるには、あと何年修行が必要だろうかと改めて、中井師を仰ぎ見る気がした。
この言葉を読んで間もなく、朝日新聞の夕刊(2013年10月4日)に中井久夫のインタビュー記事が載っていた。そこにこんな言葉があった。
<私には「この患者はこんなに良くなったと自慢すると、その患者は悪くなることがある」というジンクスがあります。>
これもすごい一言である。中井師の言葉(文章)の魅力は、その深い考察力と「中井文学」とでも呼ぶべき表現の豊かさにあるのだが、その根底には精神科臨床医としての職人的な経験の蓄積がある。「この患者はこんなに良くなったと自慢する」というのは、中井師はそうは明言していないが、たとえば医師が学界で行う症例発表のことなのだろう。いくら科学的な研究の装いを纏っていたとしても、症例発表には「俺がこんなにうまく治療してやったから患者はこんなに良くなった」という自慢の臭いがつきまとう。そうした医師が陥りがちな傲慢さを中井師は、他人事としてあげつらうのではなく、自分の職人技を磨く上でのジンクスとして語っている。自慢げに患者のことを俺が直したと語る、そのことで微妙な治療関係が一気に振りだしに戻ってしまう。患者と医師の関わりは、一対一の抜き差しならぬ真剣勝負なのだということを改めて思い知らされた。
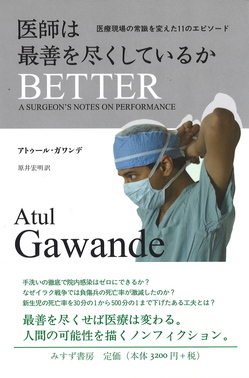 『医師は最善を尽くしているか』というノンフィクションがみすず書房から最近出た。アトゥール・ガワンデというハーバード大学の准教授を務める外科医が書いた本なのだが、とにかく面白い。著者は「ニューヨーカー」誌の専属ライターにもなっているそうで、文章が抜群によい。院内感染を防ぐために医師は日々どんな努力をしているか、新生児の死亡率を30分の1から500分の1に減らした医師はどのようにそれを実現したのか、などなど医療現場に密着し、医師の真摯な活躍ぶりを手練れの筆致で活写している。その中にこんな一行があった。
『医師は最善を尽くしているか』というノンフィクションがみすず書房から最近出た。アトゥール・ガワンデというハーバード大学の准教授を務める外科医が書いた本なのだが、とにかく面白い。著者は「ニューヨーカー」誌の専属ライターにもなっているそうで、文章が抜群によい。院内感染を防ぐために医師は日々どんな努力をしているか、新生児の死亡率を30分の1から500分の1に減らした医師はどのようにそれを実現したのか、などなど医療現場に密着し、医師の真摯な活躍ぶりを手練れの筆致で活写している。その中にこんな一行があった。
<医療は小売り業である。一時に相手できるのは一人だけである。>
これも目から鱗が落ちるような一言である。診察室での一対一の関係こそが医療のアルファであり、そしてオメガなのである。
中井師もガワンデ師も、誠実でそして何より、腕っこきの医師である。その人たちのすごい一言に打ちのめされてばかりはいられない。対人支援職として、もらったパンチは実践で打ち返すという気概を持ちたい。

- 2019年12月 (1)
- 2019年11月 (4)
- 2019年10月 (5)
- 2019年9月 (4)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (5)
- 2019年6月 (4)
- 2019年5月 (4)
- 2019年4月 (5)
- 2019年3月 (4)
- 2019年2月 (4)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (4)
- 2018年11月 (4)
- 2018年10月 (5)
- 2018年9月 (4)
- 2018年8月 (4)
- 2018年7月 (5)
- 2018年6月 (4)
- 2018年5月 (5)
- 2018年4月 (4)
- 2018年3月 (4)
- 2018年2月 (4)
- 2018年1月 (5)
- 2017年12月 (4)
- 2017年11月 (4)
- 2017年10月 (5)
- 2017年9月 (4)
- 2017年8月 (5)
- 2017年7月 (4)
- 2017年6月 (4)
- 2017年5月 (5)
- 2017年4月 (3)
- 2017年3月 (5)
- 2017年2月 (2)
- 2017年1月 (2)
- 2016年12月 (3)
- 2016年11月 (2)
- 2016年10月 (2)
- 2016年9月 (2)
- 2016年8月 (3)
- 2016年7月 (4)
- 2016年6月 (4)
- 2016年5月 (5)
- 2016年4月 (4)
- 2016年3月 (5)
- 2016年2月 (4)
- 2016年1月 (4)
- 2015年12月 (4)
- 2015年11月 (4)
- 2015年10月 (4)
- 2015年9月 (5)
- 2015年8月 (4)
- 2015年7月 (4)
- 2015年6月 (5)
- 2015年5月 (4)
- 2015年4月 (4)
- 2015年3月 (5)
- 2015年2月 (4)
- 2015年1月 (4)
- 2014年12月 (4)
- 2014年11月 (4)
- 2014年10月 (4)
- 2014年9月 (5)
- 2014年8月 (4)
- 2014年7月 (4)
- 2014年6月 (5)
- 2014年5月 (4)
- 2014年4月 (5)
- 2014年3月 (4)
- 2014年2月 (4)
- 2014年1月 (4)
- 2013年12月 (4)
- 2013年11月 (4)
- 2013年10月 (5)
- 2013年9月 (4)
- 2013年8月 (4)
- 2013年7月 (5)
- 2013年6月 (4)
- 2013年5月 (4)
- 2013年4月 (5)
- 2013年3月 (4)
- 2013年2月 (4)
- 2013年1月 (4)
- 2012年12月 (4)
- 2012年11月 (4)
- 2012年10月 (5)
- 2012年9月 (4)
- 2012年8月 (4)
- 2012年7月 (5)
- 2012年6月 (4)
- 2012年5月 (5)
- 2012年4月 (4)
- 2012年3月 (4)
- 2012年2月 (4)
- 2012年1月 (4)
- 2011年12月 (4)
- 2011年11月 (5)
- 2011年10月 (4)
- 2011年9月 (4)
- 2011年8月 (5)
- 2011年7月 (4)
- 2011年6月 (4)
- 2011年5月 (5)
- 2011年4月 (4)
- 2011年3月 (5)
- 2011年2月 (1)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |