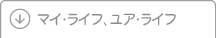5月の3日、4日、5日をプラハで過ごした。1942年、ナチス・ドイツ支配下のプラハで。
今年の連休は、ゆっくり読書三昧をしよう、と決めていた。読みたい本はいくらでもある。さて何にしようか。長編小説がいい。読んでいる間全く別世界を生きられる、上等の長編小説がいい。ローラン・ビネの『HHhH』を選んだ。
主人公は、ラインハルト・ハイドリヒ。ハインリヒ・ヒムラーの片腕として、ナチス・ドイツの政治警察権力の頂点に立ち、ユダヤ人大量虐殺を実質的に立案し、推進した中心人物である。その冷酷無比な言動により、『金髪の野獣』と渾名され、『第三帝国でもっとも怖れられた男』と言われた。
この小説の『HHhH』という奇妙な題名は、当時、親衛隊内部で囁かれていた「Himmlers Hirn heist Heydrich」という言葉から取られている。すなわち、「ヒムラーの頭脳はハイドリヒと呼ばれる」。
1941年、ヒトラーの軍事的恫喝と英仏の弱腰外交により、チェコスロバキアは共和国としての解体を余儀なくされ、チェコとスロバキアに分裂していた。スロバキアは何とか中立国として独立を保ったが、チェコはベーメン・メーレン保護領という名称でナチス・ドイツの支配下に置かれた。9月23日、ハイドリヒは、ヒトラーによりベーメン・メーレン保護領の副総督に任ぜられ、プラハに赴任する。
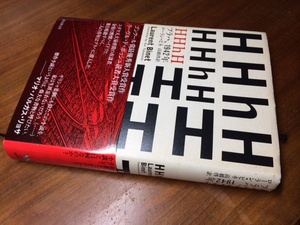 ロンドンには、ベネシュ大統領率いるチェコスロバキア亡命政権があった。歴戦のレジスタンスの勇士たちもロンドンに集結していた。
ロンドンには、ベネシュ大統領率いるチェコスロバキア亡命政権があった。歴戦のレジスタンスの勇士たちもロンドンに集結していた。
「ハイドリヒを暗殺せよ」
ベネシュによってヨゼフ・ガプチークとヤン・クビシュという2人のパラシュート部隊員が選ばれる。2人は数ヶ月に及ぶ周到な訓練と準備を経て、1941年12月28日、闇に紛れてプラハ郊外にパラシュートで降り立つ。チェコ国内の何人ものレジスタンスと連絡を取り、匿われながら、ハイドリヒ暗殺計画が進められていく。
1942年5月27日、自宅からプラハ城の執務室にメルセデス・ベンツに乗って向かうハイドリヒを暗殺部隊は捉える。最初の一撃を狙ったガプチークの自動小銃は不覚にも故障で不発に終わるが、クビシュの放った手榴弾が直近で炸裂し、ハイドリヒは重傷を負う。ハイドリヒは1週間後に病院で息を引き取った。
ハイドリヒ暗殺に怒り狂ったヒトラーは常軌を逸する残虐な報復に出る。チェコ全土に戒厳令を敷き、無実の100数十人が射殺された。それでも物足らず、プラハ郊外のリディツェ村が「暗殺部隊を匿った」として生け贄にされる。200人あまりの村人がその場で虐殺され、女性と子どもは強制収容所に送られた。村全体に火が放たれ、一軒残らず焼き尽くされた。
ガプチークたち暗殺部隊は、何とか逃げ延びて、プラハ市内の教会の地下納骨堂に潜んでいた。しかし、ナチスの執拗な捜索と仲間の一人の密告により、潜伏場所を発見され、1942年6月18日、壮絶な銃撃戦の末に英雄的な最期を遂げる。
『HHhH』は、この暗殺計画の経過を克明に追って行く。だから小説といっても、素材はすべて歴史的事実である。ローラン・ビネは、この事件に関する集められるだけのあらゆる資料に当たり、事実経過を詳述していく。当時の国際情勢や戦況についても、随所で生の資料を駆使して解説が加わる。この部分を読めば、『HHhH』は、とても新人の作品とは思えない手練れの歴史小説と賛嘆を禁じ得ないのだが、それだけでは、この作品を半分しか評価していないことになる。ローラン・ビネは、歴史とは何か、それを小説として書くとは如何なることなのか、ということを気恥ずかしいくらいのナイーブさで自らに問いかけ、その問いそのものを、この小説の結構の中に織り込んでいく。
歴史的事件を小説にしようとすると、どうしても資料では確定できないディテールが浮かび上がってくる。ハイドリヒは、もともとは空軍士官の出身で優秀なパイロットだった。秘密警察の要職に上り詰めてからも、パイロットとしての矜持を捨てきれず、1941年7月2日、メッサーシュミットを自ら操縦して、ソ連領空内で派手な空中戦を演じた末、撃墜されてしまう。ハイドリヒは命からがら不時着して何とか友軍に救出されるのだが、このニュースを聞いたヒムラーは、激怒する。その場面をローラン・ビネは、こう描写する。
「それはヒムラーの顔面に平手打ちを浴びせるようなものだった。彼の頬に血が昇り、頭蓋骨のなかで脳みそが膨張するのを感じた」
この小説は入れ子構造になっていて、ハイドリヒを巡る歴史小説を書いている「僕」がいて、その歴史小説が提示されるとともに、時々、それを「僕」が恋人のナターシャに読み聞かせるという場面が挿入される。ヒムラーに関するこの描写を読み聞かされたナターシャは、こう言う。
「『頬に血が昇り』とか『頭蓋骨のなかで脳みそが膨張する』とか、なんなのこれ?やっぱり創ってるんじゃない!」
資料だけでは確定できないディテールを小説家は想像力と筆力で補うことができる。しかし、それは所詮作り物であり、歴史への裏切りではないのか。では、出典が確定できる資料だけを継ぎ合わせるだけで歴史は書けるのか。そもそも元資料そのものだって、その書き手が「描写した事実」なのだ。
歴史を語ることへの渇望と逡巡が撚り合わさって、見事な傑作に結実した。そして、戦争を知らない、1972年生まれのローラン・ビネの、レジスタンス戦士たちへの篤実なオマージュが全編の基調をなしている。




- 2019年12月 (1)
- 2019年11月 (4)
- 2019年10月 (5)
- 2019年9月 (4)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (5)
- 2019年6月 (4)
- 2019年5月 (4)
- 2019年4月 (5)
- 2019年3月 (4)
- 2019年2月 (4)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (4)
- 2018年11月 (4)
- 2018年10月 (5)
- 2018年9月 (4)
- 2018年8月 (4)
- 2018年7月 (5)
- 2018年6月 (4)
- 2018年5月 (5)
- 2018年4月 (4)
- 2018年3月 (4)
- 2018年2月 (4)
- 2018年1月 (5)
- 2017年12月 (4)
- 2017年11月 (4)
- 2017年10月 (5)
- 2017年9月 (4)
- 2017年8月 (5)
- 2017年7月 (4)
- 2017年6月 (4)
- 2017年5月 (5)
- 2017年4月 (3)
- 2017年3月 (5)
- 2017年2月 (2)
- 2017年1月 (2)
- 2016年12月 (3)
- 2016年11月 (2)
- 2016年10月 (2)
- 2016年9月 (2)
- 2016年8月 (3)
- 2016年7月 (4)
- 2016年6月 (4)
- 2016年5月 (5)
- 2016年4月 (4)
- 2016年3月 (5)
- 2016年2月 (4)
- 2016年1月 (4)
- 2015年12月 (4)
- 2015年11月 (4)
- 2015年10月 (4)
- 2015年9月 (5)
- 2015年8月 (4)
- 2015年7月 (4)
- 2015年6月 (5)
- 2015年5月 (4)
- 2015年4月 (4)
- 2015年3月 (5)
- 2015年2月 (4)
- 2015年1月 (4)
- 2014年12月 (4)
- 2014年11月 (4)
- 2014年10月 (4)
- 2014年9月 (5)
- 2014年8月 (4)
- 2014年7月 (4)
- 2014年6月 (5)
- 2014年5月 (4)
- 2014年4月 (5)
- 2014年3月 (4)
- 2014年2月 (4)
- 2014年1月 (4)
- 2013年12月 (4)
- 2013年11月 (4)
- 2013年10月 (5)
- 2013年9月 (4)
- 2013年8月 (4)
- 2013年7月 (5)
- 2013年6月 (4)
- 2013年5月 (4)
- 2013年4月 (5)
- 2013年3月 (4)
- 2013年2月 (4)
- 2013年1月 (4)
- 2012年12月 (4)
- 2012年11月 (4)
- 2012年10月 (5)
- 2012年9月 (4)
- 2012年8月 (4)
- 2012年7月 (5)
- 2012年6月 (4)
- 2012年5月 (5)
- 2012年4月 (4)
- 2012年3月 (4)
- 2012年2月 (4)
- 2012年1月 (4)
- 2011年12月 (4)
- 2011年11月 (5)
- 2011年10月 (4)
- 2011年9月 (4)
- 2011年8月 (5)
- 2011年7月 (4)
- 2011年6月 (4)
- 2011年5月 (5)
- 2011年4月 (4)
- 2011年3月 (5)
- 2011年2月 (1)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |